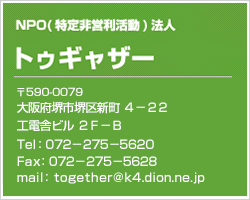2015年4月1日より施行
※食品表示法
・食品衛生法
・JAS法
・健康増進法
→ 所轄庁は「消費者庁」・・消費者を守る省庁
→ 「福祉」だから・・は通用しない できない→撤退
→ 消費者視点の法律 消費者委員会が内容を審議
■ポイント
☆アレルゲンを明記
・違反表示を一個人が申し入れできる
・罰則の強化
・機能性表示食品の制度を創設
■窓口
・今のところ保健所・農政局両方にいかなければ・・
(法律すべてを網羅できる人材がまだ育っていないため)
・取り締まり窓口ははっきりと決まっている
・通報→立ち入り検査
※公布後経過措置5年
→ それ以内に確実に表示を変えておく
■重点ポイント
・食品の製造・加工・輸入業・中間支援団体・バザー販売の中間支援団体も「食品関連事業者等」
・「アレルゲン」明記=最重要課題
義務は特定原材料7品目
準ずるもの20品目 大豆を表示するのであれば、後19品目も表示する
「アレルゲンの対象範囲(義務7品目)」を表示しておくほうが」
コンタミネーションとは?
同作業所でアレルゲンを使用していないか、それが製造工程上で紛れ込んでいないか
特定原材料使用していない≠特定原材料を含まない
「本商品の製造ラインでは乳・小麦・卵を含む商品を生産しております」と表示
・・・アレルギーのある方は買わない リスクヘッジにはなるが・・・
できれば、製造ライン上混じることのないようにする努力を!
第5条第1項
食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をしてはならない。
間違った表示をしたと気付いた場合は、自主回収
第8条第1項
立ち入り検査の場合・・・
「商品仕様書」「原材料規格証明書」「検査成績書等」の提出を求められる
第12条
食品表示の監視・是正の複線化
第17条第18条第19条
罰則 3年以下の懲役・300万以下の罰金
原産地の虚偽・立ち入り検査の拒否も・・・
とにかく、違反に気付いたら、自主回収を!
■食品表示基準の主な変更点
◆栄養成分表示の義務化の概要
・対象 あらかじめ包装されたすべての加工食品
→2020年3月31日までに
省略が認められるのは・・・表示可能面積が小さいもの・酒類・栄養供給源小さいもの・原材料が短期間で変更されるもの・義務面積事業所のもの
・変更 カロリー→熱量 ナトリウム→食塩相当量
・表示値の設定・・「推定値」「この表示値は目安です」の表示
合理的な根拠資料から計算する
計算値の注意点・・「水分分析値」を正確に出す
間違っていたら、結局検査コストがかかることに・・
◆原材料名表示等のルールの変更
食品添加物とそれ以外の原材料は分けて表示する
◆アレルギー表示
・原則個別表示とする
繰り返しになるアレルゲン省略は可能
「原材料の一部に」→「一部に」
「、」は×「・」に変える
「卵黄」→「卵黄(卵を含む)」
「卵」ではだめ卵白は原料として使っていないから
「マヨネーズ」→「マヨネーズ(卵を含む)」
・認められる代替表記・・ミルク・バター・バターオイル・チーズ・アイスクリームのみ
「ヨーグルト」→「ヨーグルト(乳製品を含む)」
強力粉 薄力粉→(小麦を含む)が必要 「小麦粉」ならOK
スキムミルク・コンデンスミルク(乳製品を含む)
→脱脂粉乳・加藤練乳ならばOK
「乳」のアレルギー表示
「乳成分を含む」のみ
◆表示レイアウトの改善
「食品添加物以外の原材料」と「食品添加物」を分けて表示
・欄を分ける ただし、添加物「なし」はありえない 空欄はあり
・段を変える
・/ を入れる
◆プラマークは枠外 6p以上6mm以上に表示が必要なので、枠外に着く余裕を持たないといけない。
◆加工食品と生鮮食品の区別の統一
計量法の特定商品かどうかを確認
◆注意ポイント
特定原材料の表示誤りはないか・・・原料記載漏れ→以前より法律があったため、直罰
表示方法の誤り→経過措置5年
◆新法に対応する場合は、栄養表示もつける 新法と旧法が混じっているのは違法
→指導対象
■食品表示法への対策
◆適正な表示を作成するために必要な書類
商品仕様書・・配合仕様書の作成
原材料規格証明書・・・原料仕入れ業者から入手 または原料の業者に問い合わせ
検査成績書
◆期限表示の設定
客観的な試験・検査を行い、科学的・合理的に設定
微生物試験・理化学試験・・検査機関に出す・・高額なのですべてする必要はない
同じような商品は省略。厳選して2~3種類
官能検査は施設で
短すぎる期限・・販売チャンスを失う
長すぎる期限・・健康被害の危険
配合比2%以下は省略可能 それより多い場合は「混合香辛料」ではだめ
■違反の未然防止体制の確立
・「人はまちがうもの」ダブルチェック体制
・食品トレーサビリティの確保(食品の移動を把握)
入荷と出荷の記録をとっておく「いつ」「どこから」「どこへ」「何を」「どれだけ」
問屋からの入荷・・納品書の管理 またはレシートの管理
・違反発見時の対応ルールの確立
告知・自主回収・消費者対応・行政報告の判断基準・実施方法・段取りをルール化しておく
■リコール保険の加入の検討
自主回収の際、かなりの費用がかかるということを知っておく その上で検討
|